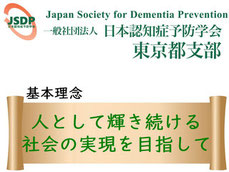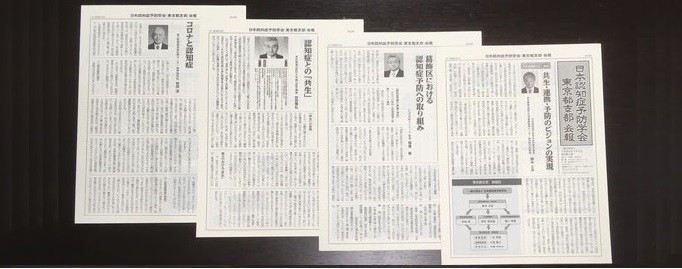第5回学術集会『大都市で実現する社会参加と認知症予防』
< ハイブリッド開催 >
お申し込みは専用サイトよりお願いいたします
認知症予防専門医/認知症予防専門士
認知症予防薬剤師/認知症予防ナース
認知症ケア専門士
< 更新単位3単位付与対象 >
日本臨床衛生検査技師会
認定認知症領域検査技師
< 10単位付与対象 >
↓↓↓ 画像をクリックすると専用サイトへJumpします ↓↓↓
新着情報
2024年 12月 2日 第5回東京都支部学術集会の参加申込みを開始しました。
2024年 9月 30日 第5回東京都支部学術集会 のご案内を掲載しました。
2024年 5月 9日 会報2024年4月号を掲載しました。
2024年 2月21日 第4回 学術集会のご案内 を掲載しました。
2024年 1月30日 会報2024年1月号を掲載しました。
2024年 1月10日 第12回 (2023年度第4回) Web講演会のお知らせ を掲載しました。
2024年 1月10日 2022年度 第4回Web講演会(第8回開催) を過去開催
アーカイブに追加しました。※ご視聴は東京都支部会員のみ
Web講演会開催のお知らせ
桜花爛漫の候、東京支部会員ならびに関係の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。緊急事態宣言が解除され4月を迎えたとはいえ、コロナ感染拡大への懸念は払拭できず、3密回避と自覚ある行動が求められている中で、東京都支部では新しい取り組みとしてWeb講演会を企画しました。講演は年間4回を予定していますが、いずれもその内容はわかりやすくかつ現場で役立てて頂けるものを立案しました。
各講演会は2部構成となっており、第1部は認知症予防専門士の資格取得を目指す皆様や認知症に関する知識をブラッシュアップしたい皆様に向けて、「認知症予防専門士テキストブック」の内容を勘案した講演となっております。
第2部は地域で認知症予防活動に積極的に取り組まれている皆様に依頼し、現場の貴重な活動内容を含めた講演をお願いしています。2021年度は、認知症予防のためのリハビリテーションやトレーニング、ダンスなどに取り組まれている講師の皆様や認知症カフェ・家族会の立ち上げ・運営に経験が豊富な講師をお招きしました。
オリンピックの開催も不透明な中、混沌とした社会情勢ではありますが、皆様方とともに東京都支部の理念である、人として輝く続ける社会の実現を目指していきたいと考えます。今年度も引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
2021年 4月 1日
支部長 鈴木正彦 Web講演会ページへ
支部長挨拶

鈴木 正彦
日本認知症予防学会
理事・東京都支部長
2019年末から世界中で猛威を振るったCOVID-19でしたが、ここにきて感染者数の減少と、2類から5類への取り扱いの変更により、パンデミックは社会的には若干落ち着きを取り戻しつつあるのではないかと感じております。こうした未曾有の状況下ではありましたが、東京都支部は理事の先生方や事務局スタッフのお力添えを得て着実な前進を遂げることができました。そこでこれまでの支部の歩みを総括し、その概要についてご紹介したいと思います。
まず日本認知症予防学会の3本の柱について再確認したいと思います。一つ目はエビデンスの創出です。これは学会主導の大規模な治験、予防ツールの検証、そして予防活動の実践・普及が含まれます。2つ目は人材の育成です。
これは認知症予防専門士、認定認知症領域検査技師、認知症予防専門医、認知症予防専門薬剤師、認知症予防専門看護師の育成を指します。そして3つ目が地域連携の実現です。これは多職種が意見交換できる場の提供や地区別活動(支部活動)が包含されます。この3つの柱を基軸として認知症予防学会は職種を超え,予防の観点からの認知症対策を考え,早期発見と治療,そして予防につなぐことを目的として活動しています。
東京都支部はこのような本部活動をサポートする形で2019年8月に発足しました。その基本理念は、人として輝き続ける社会の実現を目指して、としています。2019年6月18日に政府が提言した2025年までの施策を盛り込んだ新大綱を基軸に、「誰もがいくつになっても活躍できる生涯現役社会の実現に向けて全力を尽くす」ことを目標とし、「共生と連携と予防 つながろう!東京」を活動のスローガンとしています。そして認知症の人と家族の視点を重視し、増大する社会的コストの抑制を勘案しながら、認知症の発症と進行の抑制を目指し、認知症の病態機序を解明するためシーズを収集し、予防・診断・治療法を探索できるよう社会に貢献することを目標としています。そして、老老、認認、独居、経済的困窮、BPSD対応等の諸問題を掘り下げ、認知症になっても住み慣れた場所で生涯を全うできるよう、会員一同の英智と実践をもって認知症予防活動を実践したいとスタッフ一同考えています。
そこでコロナ禍における具体的な活動内容についてご紹介させて頂きます。まず年に1度開催する都支部主催の学術集会についてです。第1回学術集会(つながろう!東京)は東京大学脳神経内科准教授岩田淳先生に大会長をお願いし2020年2月22日に開催予定でありました。しかしながらパンデミックの影響により延期を余儀なくされ、2021年6月にパシフィコ横浜での第10回日本認知症予防学会学術集会に組み込む形でようやく開催することができました。第2回学術集会(予防と共生、次の段階へ)はやはりコロナ禍のため完全WEB配信となりましたが2022年3月12日に大会長である東京慈恵会医科大学精神神経科教授繁田雅弘先生の多大なるご尽力を持って開催されました。第3回学術集会(地域の現場から発信する認知症予防)は副支部長でむすび葉クリニック渋谷副院長荒川千晶先生のリーダーシップのもとで2023年3月4日ライブとオンデマンド配信にて開催されました。
次にWEB講演会についてです。これは年に4回開催予定で前半が認知症予防専門士テキストブックに沿った講義で後半が認知症予防に関する取り組み事例を紹介する形式を取ってきました。2021年4月17日に第1回のWEB講演会を開催し2023年4月の配信で計9回目を迎えています。いずれの回もプラクティカルな内容で構成されており視聴者からも大変好評を得ております。
そして会報についてですが、これは年4回の季刊誌として発行し、都支部ホームページ上でも無料で公開しています。2023年4月現在10回の発刊を数えていますが、これまでの主要なテーマは、コロナと認知症、国家戦略としてのフレイル予防、葛飾区における認知症予防への取り組み、アルツハイマー病の疾患修飾療法の現況と展望、認知症との共生、等でいずれもアクセス数が多く、関心度の高さを示しています。
地域連携活動しては認知症カフェを中央区にて2021年度から毎月開催し、2023年3月26日現在で16回の開催に至っています。毎回のテーマは身近な話題が多く、またヨガや脳トレ、訪問診療や在宅診療といった多岐にわたる話題を提供しているのが実情です。以上の全ての情報はホームページ上でどなたでも24時間時間を気にすることもなくアクセス可能ですし、また東京都支部の会員資格も無料で登録できますので皆様の積極的な御参加をお待ち致しております。
東京都支部は発足間もなくしてCOVID-19パンデミックに見舞われましたが、多くの方々からのご支援を頂き活動して参りました。東京都から発信できる認知症予防のためエビデンス創出、専門医や専門士などの人材育成、多職種協働・地域連携を発展させこれからも認知症予防の普及に取り組んで参ります。一人一人が認知症を良く理解し、認知症と共生できる社会を実現すべく、関係各位の皆様の協力を頂きながら、認知症の一次予防から三次予防まで全ての段階において高みを目指していく所存です。当学会の専門医、専門士、専門看護師等の資格更新単位がWEB等講演の受講により付与されますし、東京都在住でなくても入会できます。一人でも多くのサポーターが東京都支部の財産と考えておりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
2023年 4月10日